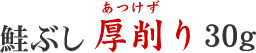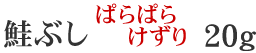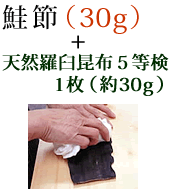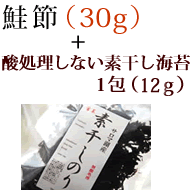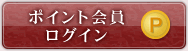●食べてもおいしい、鮭節(さけぶし)
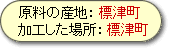
鮭の水揚げ高日本一を羅臼町と競い合うのが、おとなり標津町。
「うまいそばが食べたい」と、「標津産そばづくり研究会」の田村さんが試行錯誤の末に
完成させたのがこの 鮭ぶし <知床華ふぶき>。
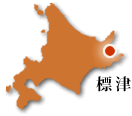 しかしながら、単純に「鮭を削り節」にしたわけではありません。 しかしながら、単純に「鮭を削り節」にしたわけではありません。
カツオ節の伝統製法「手火山(てびやま)造り」をサケ節でも再現するために、工場長となるスタッフを「カツオ節の本場」である静岡県焼津の老舗に長期派遣。そう、まさに修行させたのです。
●鮭ぶし、手火山式は 50日間の工程。
焼津の老舗カツオ節工場のいぶし釜「手火山式焙乾(ばいかん)炉」を、寸分の狂いもなく再現した田村社長。
そして、修行したカツオ節工場から譲り受けたという「50年は経っている」セイロが自慢です。
鮭ぶしが出来上がるまでに50日間。
時間と手間ひまがかかる製法なのでたいへん生産量は少ないのですが、しかしこの「鮭ぶし・華ふぶき」には大量生産のものにはない「風味と香ばしさ」があります。
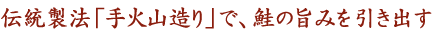
江戸時代の昔から、この手火山式の焙乾(いぶして乾燥)が最良の方法であると言われていたそうです。
手火山は「直火式」なので香りが強く、良質な削り節づくりにはかかせません。
しかしながら手火山は、たいへん手間のかかる方法であり、いまでは日本でも数社でしか行っていません。
木製のせいろに並べたゆでたサケを、自前の「手火山式焙乾(ばいかん)炉」の上に積み上げ、ミズナラの薪でいぶします。
それから薫製室で20日間いぶして乾かし、さらに冷蔵庫で1カ月じっくりと熟成させてから削っていきます。
 鮭節は、グルタミン酸主体のすっきりした味。 鮭節は、グルタミン酸主体のすっきりした味。
サケ節のうま味成分は「グルタミン酸」がメインです。
イノシン酸が多いカツオ節にくらべると、たいへんすっきりして甘みがあります。
カツオ節とブレンドしてだしを取るのも良いそうです。
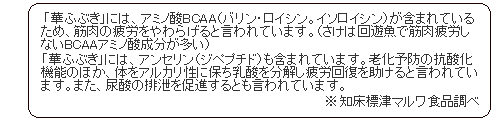
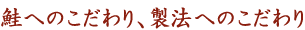
 「標津産にこだわり、製法にこだわり、地道に本物の味を作っていきたい」と鮭節への想いを語る、知床標津マルワ食品の田村社長。 「標津産にこだわり、製法にこだわり、地道に本物の味を作っていきたい」と鮭節への想いを語る、知床標津マルワ食品の田村社長。
鮭の旨みを最大限に引き出す昔ながらの伝統製法で、じっくりと丁寧に仕上げた「鮭節」の独特のうまみと風味をお楽しみください。
鮭ぶしの楽しみかた
・冷奴やおひたしに直接かけて。
・ご飯にまぜておにぎりに。(醤油で味付けおにぎりの具材に)
・ご飯に焼き鮭の身をのせ、鮭節で出汁をとり、塩で味を調え鮭茶漬けの完成。
・お好み焼きや、たこ焼きに。焼うどんや焼そばの仕上げにも。
・おでんやつけ麺にふりかけとして。
・出汁に。(蕎麦やうどんのつゆに、だし巻き卵等)
『鮭節のだしの取り方』は ⇒ こちらをご参考(カツオ節と昆布) |


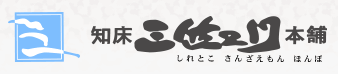

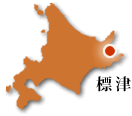 しかしながら、単純に「鮭を削り節」にしたわけではありません。
しかしながら、単純に「鮭を削り節」にしたわけではありません。
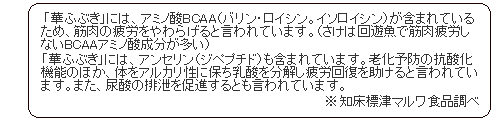
 「標津産にこだわり、製法にこだわり、地道に本物の味を作っていきたい」と鮭節への想いを語る、知床標津マルワ食品の田村社長。
「標津産にこだわり、製法にこだわり、地道に本物の味を作っていきたい」と鮭節への想いを語る、知床標津マルワ食品の田村社長。 ●
● ●
●